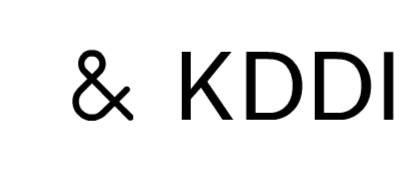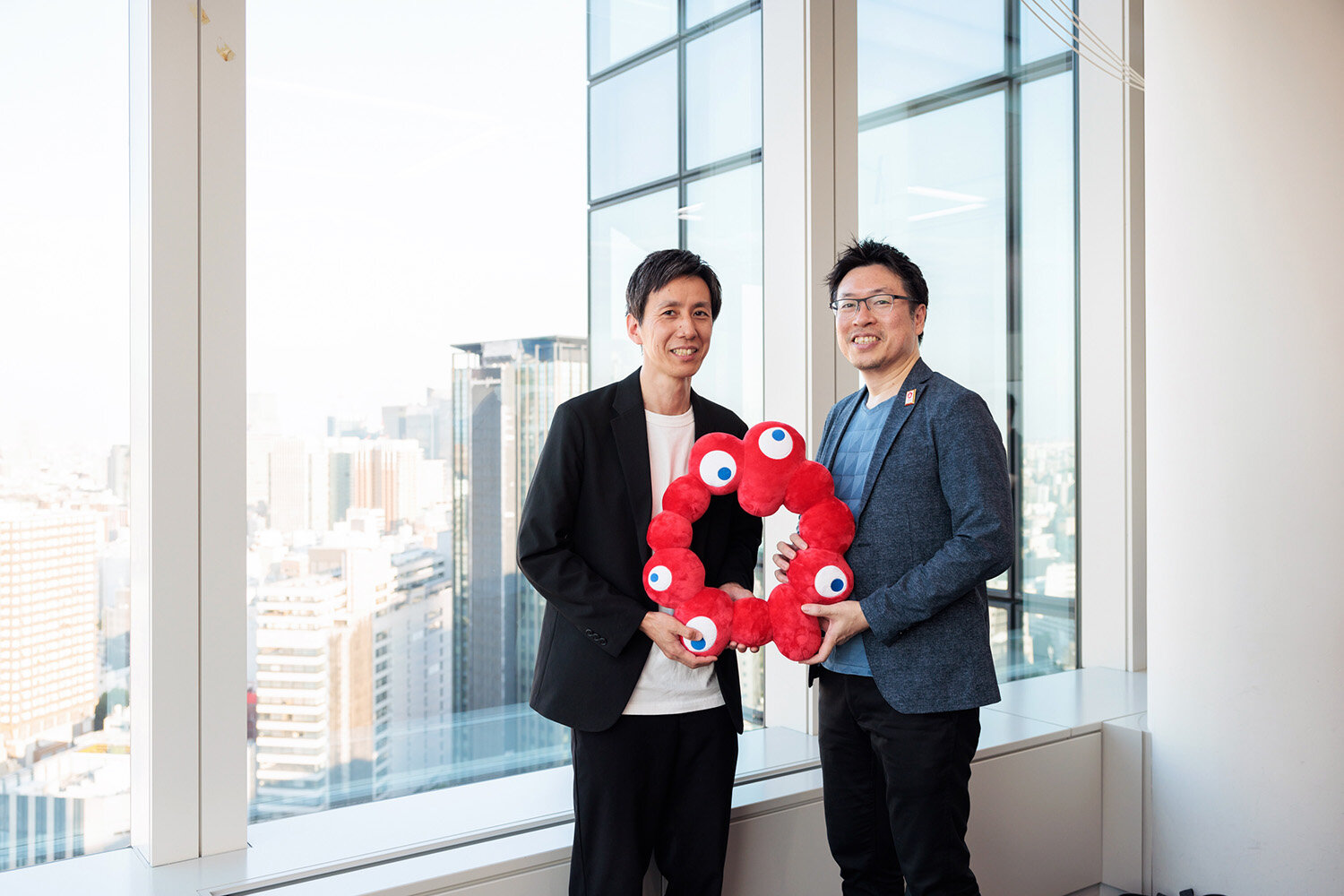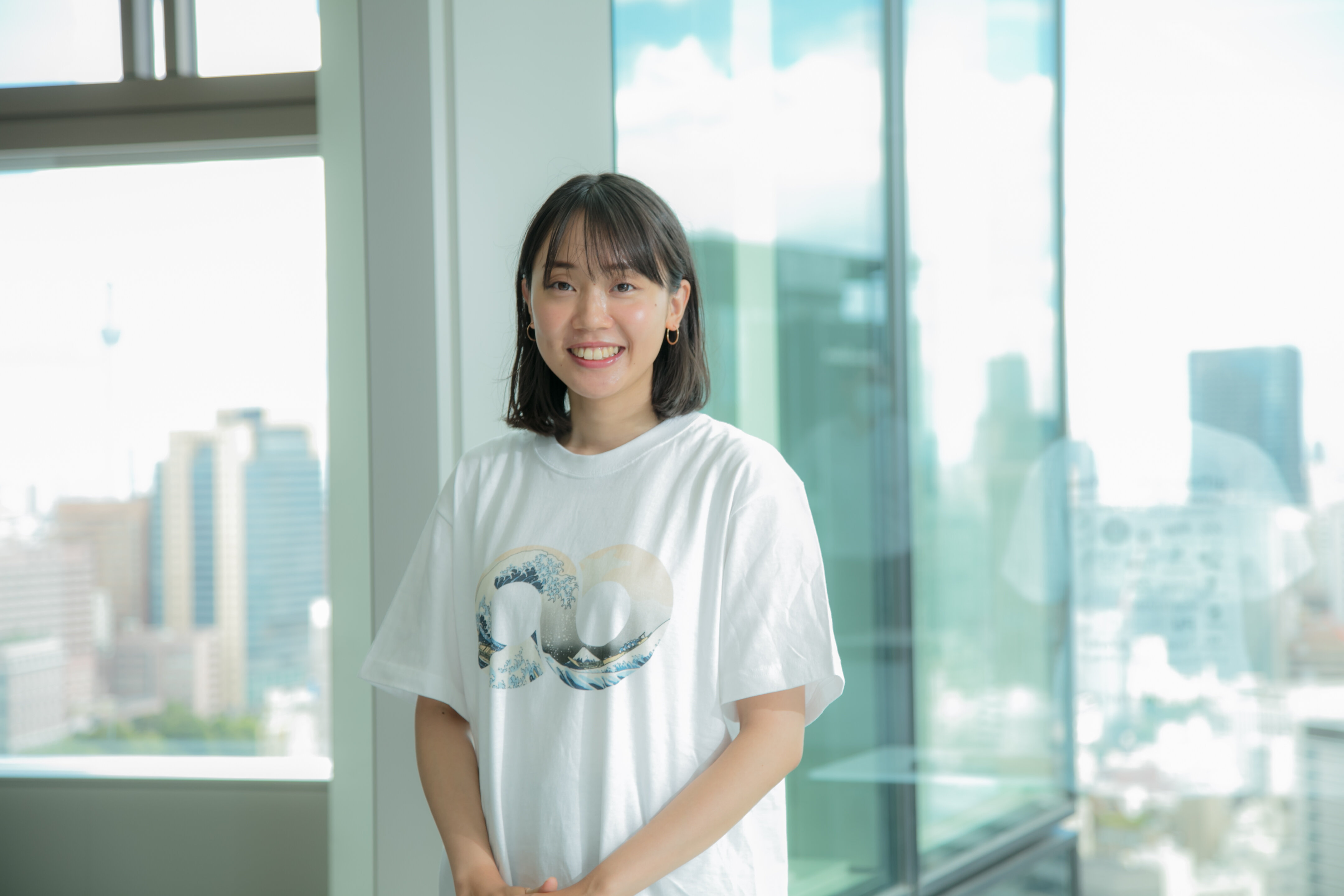技術・サービス
2025/09/30
ゼロからたった1年で「auサポート AIアドバイザー」をつくれた理由

KDDIではゼロからたった1年で、デジタルヒューマンを活用したオンラインサポートサービス「auサポート AIアドバイザー」をつくり上げ、提供を開始しています。サービスの企画・開発にかかわった4名のキーパーソンに、お客さまへ新しい体験価値を届けるまでの舞台裏を伺いました。
目次
■インタビュイー略歴
-

小寺 優輝
- カスタマーサービス本部 カスタマーサービス企画部
-

藤原 拓哉
- カスタマーサービス本部 カスタマーサービス企画部
-

仙崎 萌絵
- DXデザイン本部 デザインセンター
-
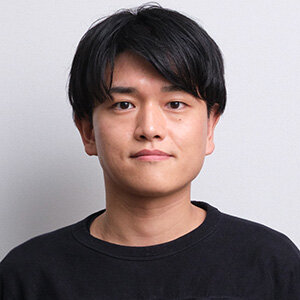
川崎 莉央
- 情報システム本部 DXシステム2部
1年間の開発期間で多くのユーザーが納得する品質を
「auサポート AIアドバイザー」の開発経緯を教えてください。
小寺:カスタマーサービス企画部は、お問い合わせ・サポートチャネルのDX化を推進している部署です。これまでもさまざまな形でお客さまの体験価値向上に取り組んできており、近年はデジタルシフトを推進してきました。今後もデジタルシフトを促進していくためには、サポート体験のさらなる価値向上や新たな体験価値が必要です。そうした背景のもと、AIを活用したデジタルヒューマンの導入検討が始まりました。
市場調査を行ってみると、海外ではすでに多くの企業がデジタルヒューマンを導入しています。日本国内でも今後導入が進んでいく可能性が高く、他社に先駆けていち早く取り入れる必要性があると感じました。
サービスリリースまでの期間は、検討期間を含めて1年間。検討当初は不安が大きかったですが、すぐにプロジェクトメンバーを巻き込んで動き出しました。特に開発を担当してくれたコア技術統括本部の川崎さんとは、かなり早い段階から連携しました。
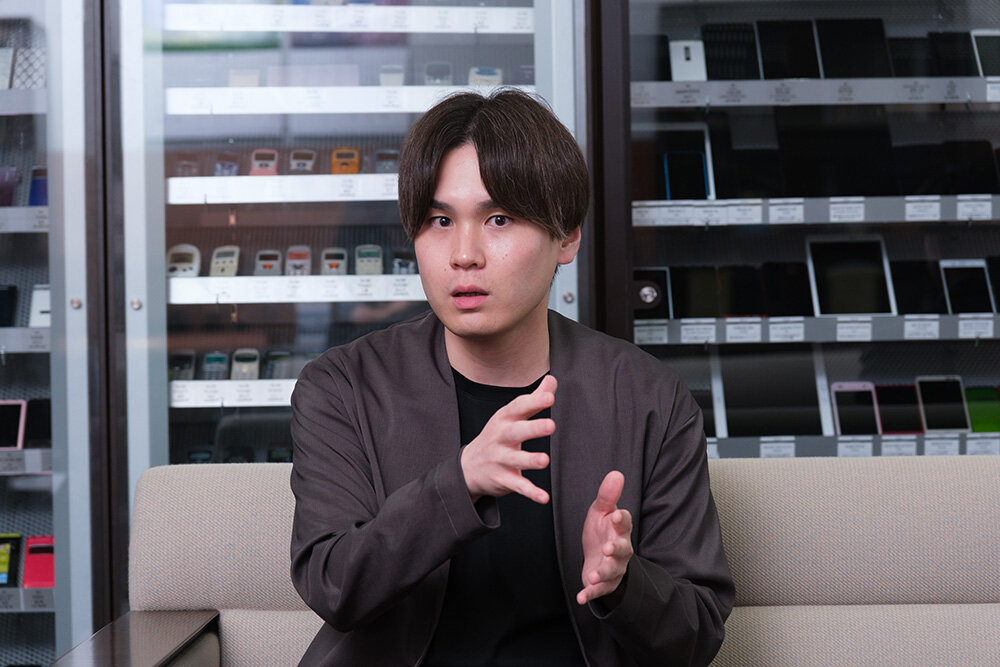
▲カスタマーサービス本部 カスタマーサービス企画部 小寺
川崎:今回のプロジェクトの難しいところは「1年」という開発期間の短さでした。企画からゼロベースでサービスを立ち上げる期間としては短く、またデジタルヒューマンという新しいサービスのため手探りの部分も多く、難易度の高いプロジェクトだと感じました。
ただ、我々のサービスの先には多くのお客さまがおり、「au」というブランドを背負っている以上、開発期間の短さを言い訳に中途半端な機能や品質のサービスを提供することはできません。 できるかぎり用意周到・準備万端の状態でプロジェクトに臨むため、リリース日から逆算したスケジュールを作成し、いつまでに、何をすべきなのかを見える化しました。

▲情報システム本部 DXシステム2部 川崎
川崎:とはいえ時間が限られていることは変わりません。限られた時間の中でカスタマーサービス企画部からの期待に応えるサービスをつくるにはどういうシステム構成にすべきか、かなり知恵を絞りました。
システム構成を考えた後、急いでプロトタイプを作成し、デジタルヒューマンが実際に実現可能かを判断する判定会に臨みました。機能の動作や挙動の確認に関するチェックリストが埋まるごとに、求められている基準に応えられるという確信が強まっていきました。
これで開発の目途も立ち、後続工程を仙崎さんにつなげることができました。
デジタルであっても親しみやすく お客さまの思いと命を吹き込む
デジタルヒューマンのビジュアルなどを担当されたとのことですが、どのようなプロセスでつくられていったのでしょうか。
仙崎:お客さまがどのようなサポート体験を求めているのかを調査し、そのニーズに応えるためにどのような価値を提供すべきかという視点で、体験のコンセプトを検討しました。
調査の結果、デジタルヒューマンによるサポートを必要しているのは「悩みがあったときに自分の力で解決を試みるものの、最終的には解決できず電話をかけてくださる方たち」であることがわかりました。
こうしたお客さまもデジタルヒューマンというサポート体験があれば、人に話すよりも気楽に遠慮なく相談ができるはずです。気を遣わずに気楽に話せること自体が価値につながると考え、デジタルヒューマンの体験コンセプトとしてまとめていきました。

▲DXデザイン本部 デザインセンター 仙崎
仙崎:ここから、この体験コンセプトを具現化するデジタルヒューマンのビジュアルを考案していきます。
コンセプトは「自然に話せて、気軽に相談できる auサポート AIアドバイザー」。つまり、お客さまがデジタルヒューマンと自然かつ気軽に話せることです。それを体現するキャラクターを複数案作成しました。どのキャラクターが最適なのかを決めるためにワークショップを開催し、プロジェクトメンバー間で、各キャラクターがどんなビジュアルなのか、人物としてどういう背景があるのかといった細かい設定を考えていきながら、最終的に一人に絞っていきました」。
仙崎:日本国内ではデジタルヒューマンを用いたサービス事例が少なく、お客さまにはなじみがないと思います。それでもどこか親しみやすく、気軽に話しかけてもらえるよう、ビジュアルにはかなり細かいこだわりを詰め込んでいます。お客さまも違和感なく、auサポートAIアドバイザーを受け入れられているのではないかと期待しています。
ビジュアルだけでなく、親しみやすくなるように藤原さんがさまざまなこだわりを込めてくれています。
違和感のない声と雑談 親しみやすさは細部に宿る
auサポートAIアドバイザーに込めたこだわりを教えていただけますか。
藤原:一つ目は「声」です。もともとデフォルトの音声を使用する予定でしたが、日本語のイントネーションにかなりの違和感がありました。このままではお客さまにとって不要なノイズになってしまうので、ゼロからオリジナル音声を開発しました。
また、「発音」にもかなりのこだわりを込めており、300件以上の会話パターン一つひとつ耳で確認しました。音声版のゲシュタルト崩壊を起こすくらい、苦労しながら調整しました。

▲カスタマーサービス本部 カスタマーサービス企画部 藤原
藤原:もうひとつのこだわりは「雑談」機能です。世の中のデジタルヒューマンを見渡しても雑談ができるサービスは意外と少ないです。親しみやすさを大事にしているからこそ、こうした遊びがある方がUX(ユーザー体験)も向上すると思い、こだわって導入しました。
雑談内容についても、お客さまと自然かつ柔軟に会話ができるよう生成AIの出力結果をそのまま表示しています。AIがハルシネーション(誤った回答をすること)を起こさないことに加え、不適切な会話に誘導するような攻撃にもきちんと対処できるよう調整をしているので、お客さまも安心して会話を楽しむことができます。会話の内容によっては、パーソナリティを生かした雑談もできるようプロンプトを調整しています。
新しいテクノロジーに 夢中で駆け抜けた1年間
あらためてプロジェクトを振り返ってみていかがでしょうか。
小寺:一言で振り返るなら「責任感」です。これまでもさまざまなサービスでプロダクトマネージャーを担当してきましたが、ゼロから新しいサービスをつくる経験は初めてでした。やみくもに動いても失敗することは目に見えていたので、基本どおりにタスク管理や進行管理を徹底し、開発メンバーとも密に連携をとりながら進めていきました。
川崎:今回のプロジェクトのユニークな点は企画と開発メンバーが同じフロアに集まり、物理的な距離を縮めて連携を強化させたことです。急な要件変更があったとしてもその場で確認がとれるため開発スピードが高まり、コミュニケーションの頻度・密度に応じて、プロジェクトチーム全体がどんどん一丸となっていく感じがありました。
小寺:ここまでスピード感をもって進められたのも、経営層が現場メンバーに裁量を持たせてくれたからだと思っています。直属の上長も課題が顕在化したときに的確なアドバイスを送ってくれましたし、バックアップは心強かったですね。
川崎:こうしてあらためて振り返ってみると大変なことが多かったですが、世の中でも最先端のサービスに携わることができ、すごく刺激的でした。
小寺:本当にそうですね。新しいことに夢中になって駆け抜けた1年間だったと思います。とはいえ、まだまだサービスとしては発展途上なので、今後もお客さまのお困りごとを迅速に解決できるよう、さまざまな機能を追加させてサービスを進化させていきます。